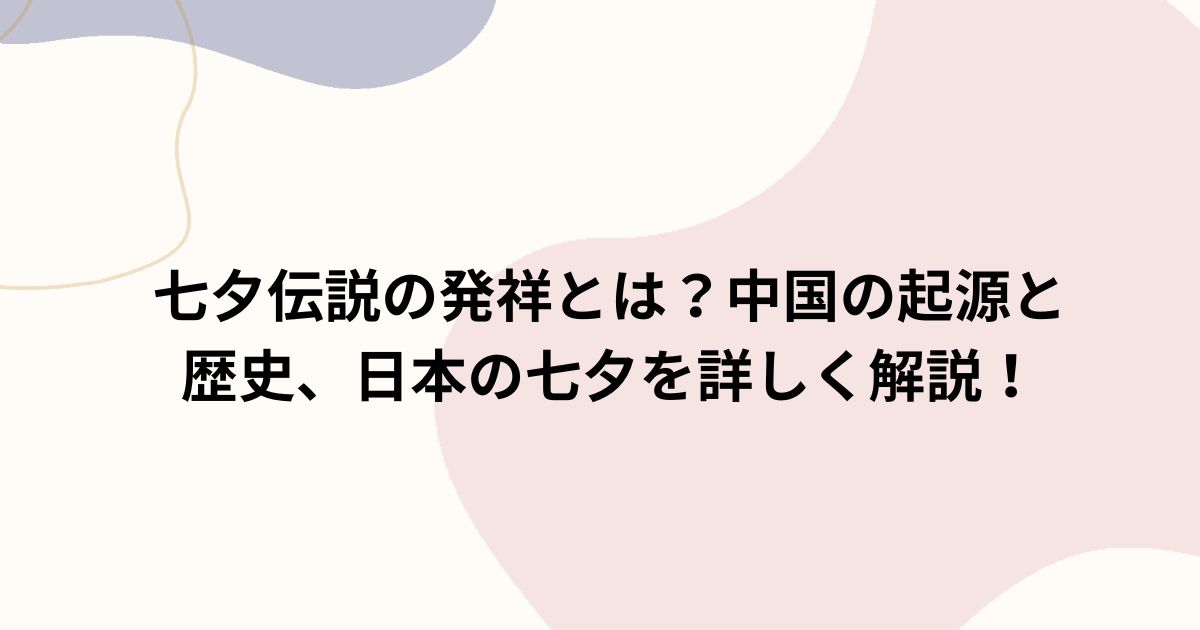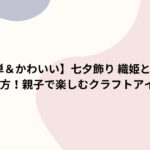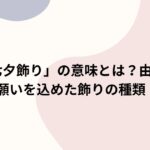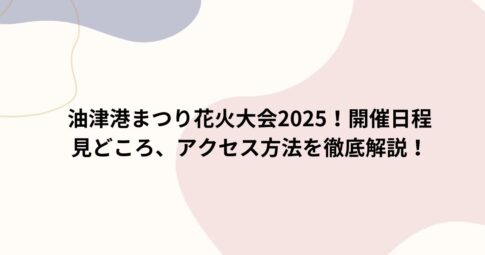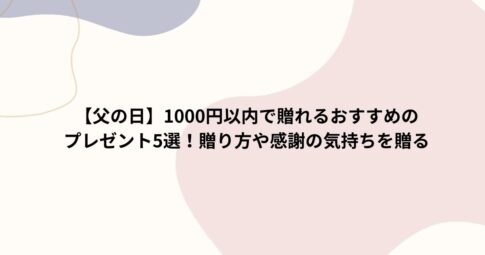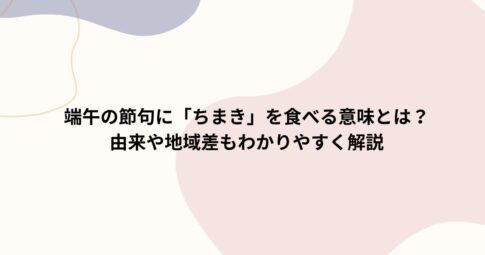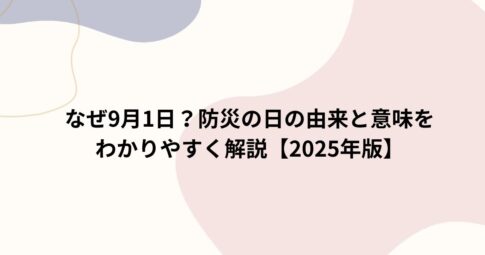はじめに
七夕は、日本をはじめとするアジア各国で広く親しまれている伝統行事です。織姫と彦星のロマンティックな伝説は多くの人に知られていますが、その発祥や歴史について詳しく知っている人は意外と少ないかもしれません。
本記事では、七夕伝説の起源や日本に伝わった経緯について詳しく解説します。
七夕伝説の発祥と起源

引用元:MaMaPLUS
七夕のルーツ:中国の「乞巧奠(きこうでん)」
七夕の起源は中国にあり、「乞巧奠(きこうでん)」と呼ばれる行事が基になっています。この行事は、織女星(織姫)と牽牛星(彦星)にちなんだものとされ、女性が手芸や裁縫の上達を願って祈る祭りでした。
日本への伝来と平安時代の宮中行事
七夕の風習は奈良時代に日本へ伝わり、平安時代には宮中行事として定着しました。この時代では、貴族たちが川のほとりで詩を詠んだり、裁縫の上達を祈願する行事が行われていました。
日本における七夕の発展
江戸時代の庶民文化への浸透
江戸時代になると、七夕の行事は庶民の間にも広がりました。特に短冊に願い事を書く風習が一般的になり、現代の七夕の原型が形作られました。
現代の七夕祭りと地域ごとの特徴
日本各地では、仙台七夕まつりや平塚七夕まつりなど、大規模な七夕イベントが開催されるようになりました。地域ごとに異なる特色を持つ七夕祭りが行われています。
七夕伝説の文化的影響
織姫と彦星の物語
七夕伝説では、天の川を隔てた織姫と彦星が一年に一度だけ再会できると言われています。この物語は、恋愛や努力の象徴として多くの文化作品にも影響を与えています。
アジア各国の七夕の違い
七夕の風習は日本だけでなく、中国や韓国、ベトナムなどアジア各国にも存在します。それぞれの国で異なる七夕の祝い方があり、文化的な多様性を感じることができます。
七夕伝説の発祥:まとめ
七夕伝説の発祥は、中国の「乞巧奠」に由来し、日本には奈良時代に伝わりました。平安時代には宮中行事として発展し、江戸時代に庶民の間でも広がりました。
現代では、日本各地で華やかな七夕祭りが開催され、織姫と彦星の伝説が多くの人々に親しまれています。
七夕の由来や歴史を知ることで、この行事の奥深さをより一層楽しめるでしょう。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪
- 「七夕飾り」の意味とは?由来や願いを込めた飾りの種類を徹底解説!
- 七夕飾りにぴったり!ちょうちんの作り方と必要な材料、アイデア集!