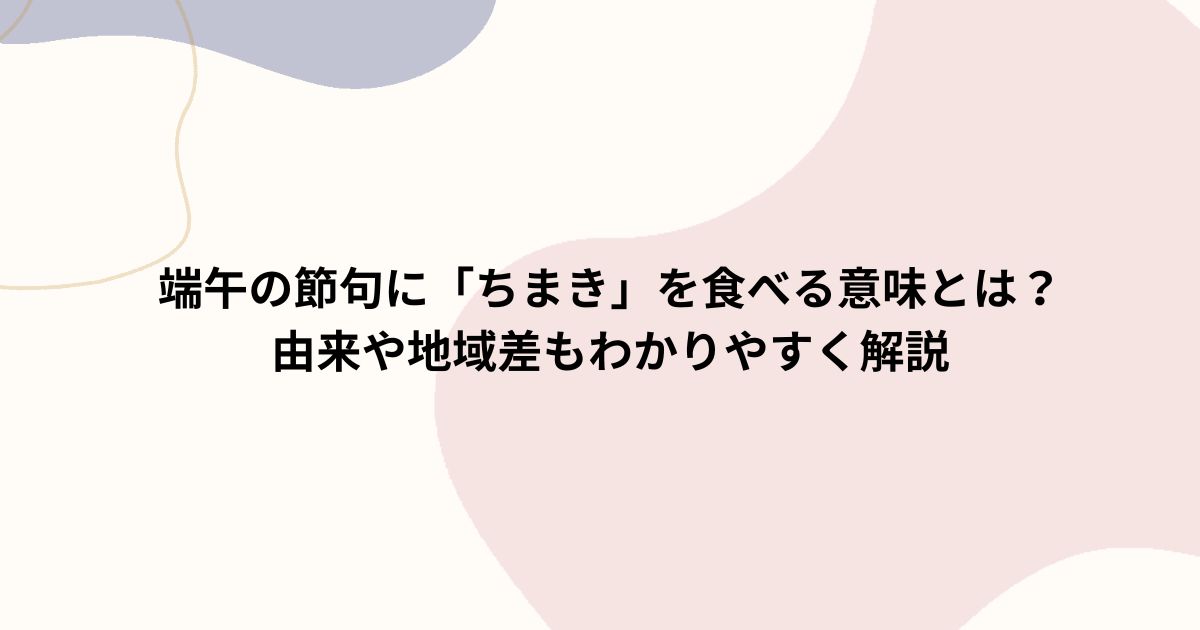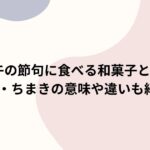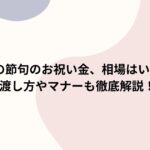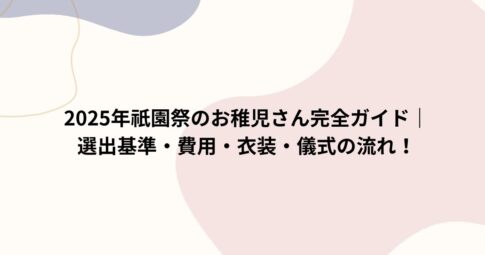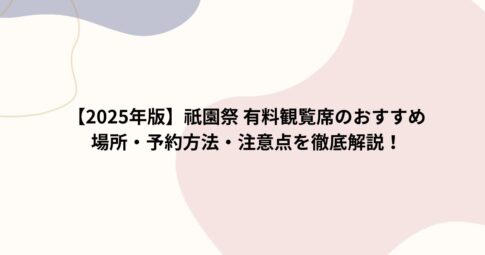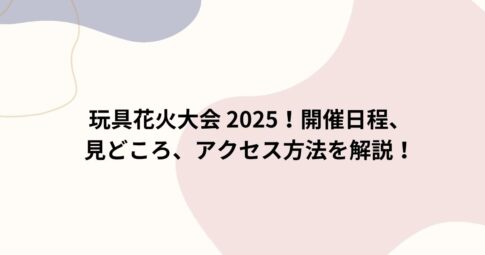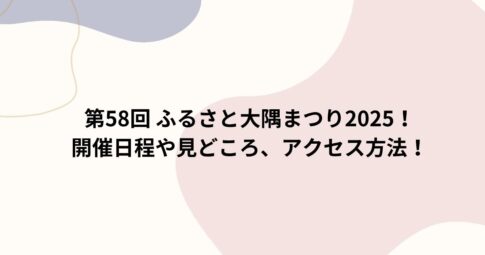はじめに
5月5日の「端午の節句」といえば、鯉のぼりや兜、柏餅が有名ですが、「ちまき」も欠かせない食べ物の一つです。けれども、「なぜちまきを食べるの?」とその意味まで知っている人は意外と少ないかもしれません。
この記事では、ちまきを食べる理由や由来、地域ごとの違いなどをやさしく解説します。これを読めば、端午の節句の理解がより深まりますよ。
端午の節句とは?背景と意味を再確認
男の子の健やかな成長を願う行事
端午の節句は、5月5日に行われる日本の伝統的な行事で、**「こどもの日」**としても知られています。特に男の子の健やかな成長や健康を願って、鯉のぼりや五月人形を飾るのが習わしです。
古代中国にルーツがある行事
実は端午の節句は、もともと中国の古代行事が日本に伝わったもの。邪気払いの風習が元になっており、日本では鎌倉時代以降、武士の家で特に大切にされるようになりました。
なぜ「ちまき」を食べるの?その意味と由来

引用元:tenki
「ちまき」は厄除けの象徴
ちまきは、笹や竹の葉で包まれた餅や米を蒸した食べ物。その包まれた形状が「災いから守る」お守りのような意味を持つとされています。食べることで、健康・長寿・厄除けを願う意味が込められています。
ちまきの由来は屈原(くつげん)の伝説
ちまきの起源として有名なのが、**中国戦国時代の詩人・屈原(くつげん)**の物語です。彼は国を憂えて川に身を投げた際、民衆が供養として川に米を投げ入れ、それが後に葉で包まれた「ちまき」の形になったといわれています。
この故事が端午の節句にちまきを供える風習の始まりとされ、日本にも伝わりました。
ちまきと柏餅の違いって?

関東は柏餅、関西はちまき文化
端午の節句に食べられる和菓子は、地域によって違いがあります。
- 関東地方:柏餅(かしわもち)が主流
- 関西地方:ちまきが中心
柏餅は、新芽が出るまで葉が落ちない柏の葉に「家系の繁栄」や「子孫繁栄」の意味が込められています。一方、ちまきは先述のように邪気払い・厄除けの意味が強いです。
素材や味の違いもポイント
柏餅はこしあん・つぶあん・みそあんなど甘い味が主流ですが、ちまきは甘いものから塩味のものまで幅広く、もち米やうるち米などを使って多様にアレンジされています。
また、中国由来の「中華ちまき(肉入り)」とは異なり、日本の端午の節句で使われるちまきは、細長い円錐形で笹の葉に包まれているのが特徴です。
現代の端午の節句でちまきを楽しむには?
市販のちまきや手作りも人気
最近では、和菓子店やスーパーで簡単にちまきを購入できます。手作りしたい方には、もち米と笹の葉、蒸し器があれば簡単に作れるレシピもたくさん紹介されています。親子で作ってみるのも、端午の節句の良い思い出になります。
ちまきを贈り物として渡すのもおすすめ
ちまきは、縁起の良い食べ物として、季節のご挨拶やちょっとした贈り物としても人気です。「無病息災」や「元気でいてね」というメッセージを添えて贈ると、より喜ばれます。
端午の節句にちまきを食べる意味:まとめ
端午の節句にちまきを食べるのは、古代中国から伝わる「厄除け」「供養」「健康祈願」の風習が背景にあります。
地域によっては柏餅が主流ですが、ちまきには深い意味が込められており、現代でも大切にされています。
伝統を知って味わうことで、子どもたちにもその由来を伝え、より豊かな節句のひとときが過ごせるはずです。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪
- 【祖父母必見】端午の節句のお祝い、孫への素敵な贈り方とマナーとは?
- 【兜は誰が買う?】端午の節句のしきたりと現代の事情をわかりやすく解説!
- 端午の節句のお祝い金、相場はいくら?渡し方やマナーも徹底解説!