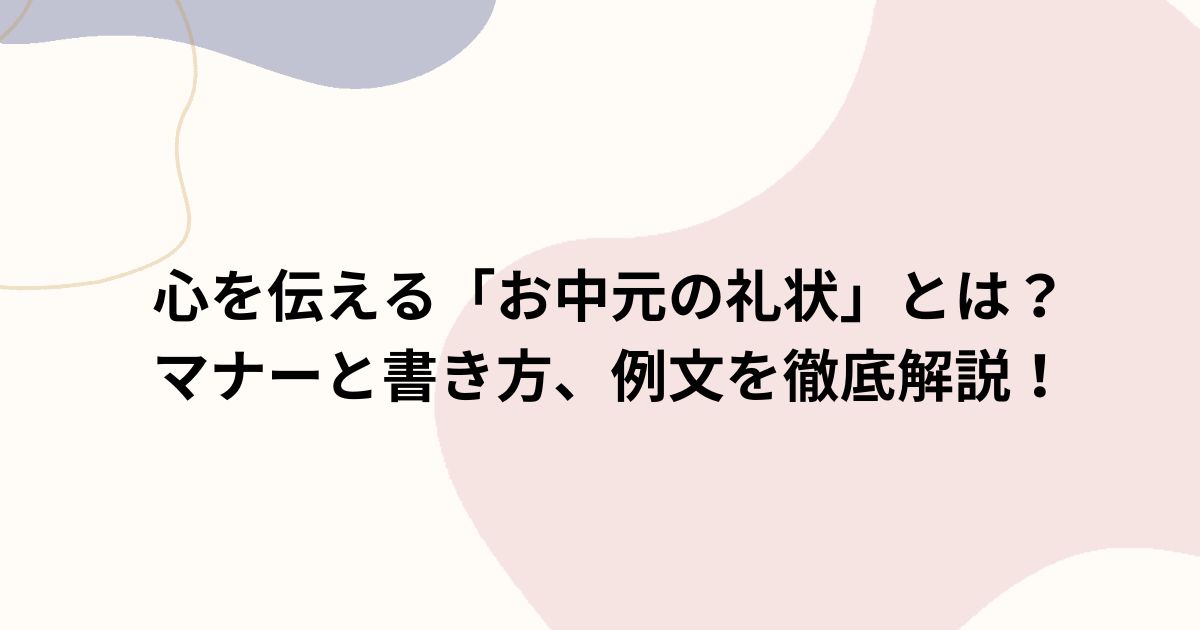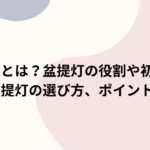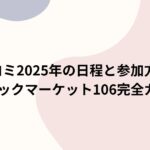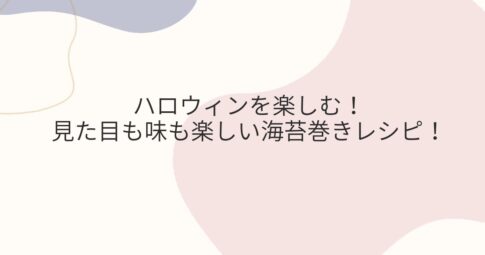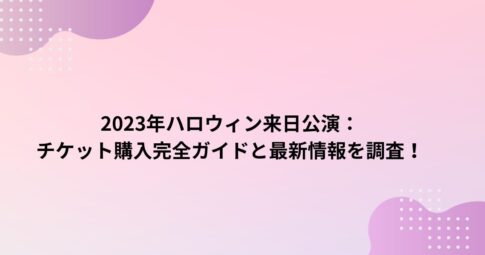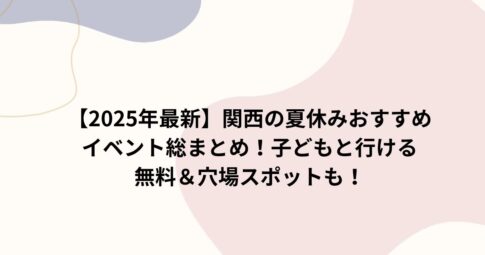はじめに
暑い季節に届くお中元は、日頃の感謝の気持ちが込められた大切な贈り物です。もらったら忘れずにお礼状を送りましょう。
この記事では、お中元の礼状の意味からマナー、実際の書き方、例文までを解説します。
お中元の礼状とは?その重要性を知ろう
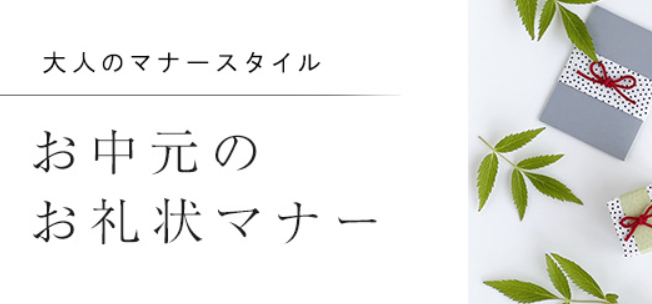
引用元:ナチュラン
お中元の礼状とは、品物を受け取ったという報告と感謝の気持ちを相手に伝えるためのものです。
お中元には「年明けから中元までお世話になりました」「暑さで体調を崩されませんように」という贈り主の思いが込められています。その気持ちに応えるためにも、お礼状は欠かせないマナーなのです。
お礼状を送ることで、贈り主は「品物が無事届いたか」「喜んでもらえたか」という気がかりも解消されます。つまり、お礼状は単なる形式ではなく、相手の気持ちに誠実に応える大切な行為なのです。
お中元の礼状の基本マナー4つを押さえよう
3日以内に出す
お中元が届いたら、まずはその日のうちに電話やメールで受け取りの連絡をしましょう。そしてお礼状は3日以内に出すのがマナーです。返礼品を贈る場合は1週間以内に手配を。
お返しは必要ない
お中元はもともとお世話になっている人へ感謝を表す風習なので、お返しをせずにお礼状のみでも問題ありません。
「もらってばかりでは…」という場合は「お返し」ではなく「贈り合う」という気持ちで品物を選びましょう。ただし、相手より高価なものを贈るのは避けましょう。
頭語と結語を必ず含める
手紙の基本である頭語と結語は必ず対で使用します。相手との関係性に応じて使い分けましょう。
- ビジネス全般:「拝啓」と「敬具」など
- 目上の人:「謹啓」と「謹言」など
- 親しい人:「前略」と「草々」など
手書きが基本
お礼状は手書きが基本です。手書きのお礼状は温かみがあり、感謝の気持ちが伝わりやすいものです。毛筆が理想ですが、ボールペンや万年筆でも構いません。鉛筆やシャーペン、水性ペンは避けましょう。
お礼状の正しい書き方と項目
お礼状には以下の項目を含めます:
- 頭語:相手に合わせたものを選びます
- 時候の挨拶:季節に合わせた言葉を使います(「盛夏の候」「猛暑の候」など)
- 健康・安否を尋ねる:「お変わりなくお過ごしでしょうか」など
- お礼と感謝:「お心のこもったお品を頂き、誠にありがとうございました」など
- 健康や息災を願う:「まだまだ暑い日が続きますので、どうぞご自愛ください」など
- 結語:頭語と対になるものを選びます
- 差出人と日付:元号を使って日付と名前を記入します
お礼状の例文集—相手別のポイント
ビジネス関係の場合
ビジネス関係者へのお礼状は、丁寧な言葉遣いと正式な形式を守りましょう。
〈会社・企業宛の例文〉
株式会社□□
代表取締役 ○○ 様
拝啓 盛夏の候、貴社におかれましては益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたびはお心のこもったお中元の御品を頂戴いたしまして、誠にありがとうございました。
暑さ厳しき折柄、皆様のご健勝と貴社の益々のご発展をお祈り申し上げますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます。
敬具
令和〇年〇月〇日
〇〇株式会社
代表取締役 ××××(氏名)
〈取引先個人宛の例文〉
株式会社□□
△△課 ○○ 様
拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、このたびは心のこもったお品をお贈りいただき、誠にありがとうございました。
平素のご支援ご協力にくわえ、このたびのお心遣いに一同恐縮いたしております。
心からお礼申し上げますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願いいたします。
時節柄、くれぐれもご自愛くださいませ。
まずは略儀ながら書中にてお礼申し上げます。
敬具
令和〇年〇月〇日
○○株式会社
△△部 ××××(氏名)
親族や親戚の場合
親族間でも礼儀は大切ですが、ビジネス文書よりは柔らかい表現を使いましょう。
〈親族宛の例文〉
○○ 様
拝啓 暑さも本番を迎えたばかりですが、皆様お変わりございませんか。
本日は、結構なお中元の品をお届けいただき、誠にありがとうございました。
家族一同大喜びで、さっそく賞味させていただきました。
いつもながらのお心遣いに感謝いたしております。
まだまだ続く暑さに、皆様どうぞご自愛ください。
略儀ながら書面にてお礼申し上げます。
敬具
令和〇年〇月〇日
×× ××(氏名)
友人や知人の場合
友人や知人へは、より親しみのある表現を使いながらも感謝の気持ちをしっかり伝えましょう。
〈友人宛ての例文〉
○○ 様
前略 暑さが増してきましたが、○○様におかれましては、お元気にお過ごしのことと存じます。
さて、このたびは嬉しいお心遣いを頂き、ありがとうございました。
さっそくではありますが、初夏の慌ただしさも忘れるほどにおいしく頂きました。
いつもながらのお心遣いに恐縮するとともに、家族ともども大変喜んでおります。
これから本番を迎える暑さゆえ、くれぐれもご自愛くださいませ。
まずはお礼まで。
草々
令和〇年〇月〇日
×× ××(氏名)
季節に合わせた季語の使い方
お礼状に季節感を出す季語は大切です。時期に合わせて選びましょう。
6月下旬:新緑、梅雨、長雨、空梅雨など
拝啓 今年は空梅雨につき、皆様ますますご健勝のことと存じます。
〇〇様には日ごろより多くのお心遣いをいただき、お礼申し上げます。
7月:盛夏、猛暑、酷暑、真夏、炎暑など
拝啓 盛夏の候、お変わりなくお過ごしでしょうか。
本日は心のこもったお中元の品を頂戴しまして誠にありがとうございました。
8月:立秋、残暑、晩夏など
拝啓 厳しい残暑が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
このたびは嬉しいお中元の品をお送りいただき誠にありがとうございました。
お礼状を代筆してもらう場合の注意点
忙しくて自分で書けない場合、代筆を頼むこともあるでしょう。その場合は以下の点に注意しましょう。
- 妻に代筆を頼む場合は、夫の名前の後に「内」と記します
- 部下に代筆を頼む場合は、上司の名前の後に「代」と代筆者の苗字を記します
- 重要な取引先や直属の上司へは、できるだけ自分で書きましょう
- 代筆の場合も必ず手書きで!
まとめ:心のこもったお礼状で関係を深めよう
お中元の礼状は形式だけでなく、感謝の気持ちを伝える大切なコミュニケーションツールです。
基本的なマナーを押さえつつ、自分らしい言葉で感謝の気持ちを伝えることで、より良い人間関係を築いていきましょう。
実際の例文を参考にしながら、相手との関係性や季節に合わせた礼状を書くことで、心のこもった感謝の気持ちが伝わります。
暑い季節だからこそ、温かいお礼状で相手に笑顔を届けてみませんか?
最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪