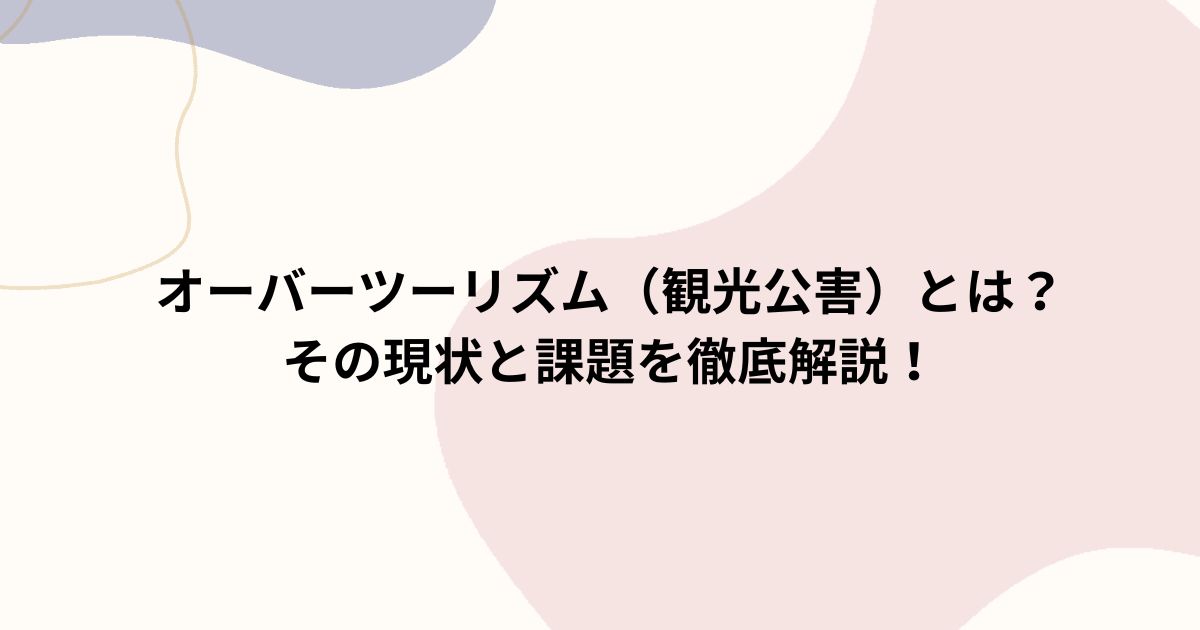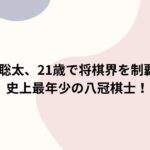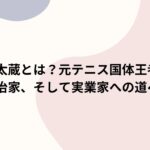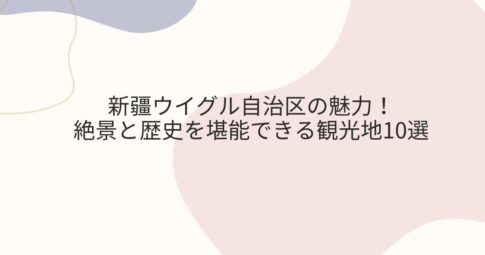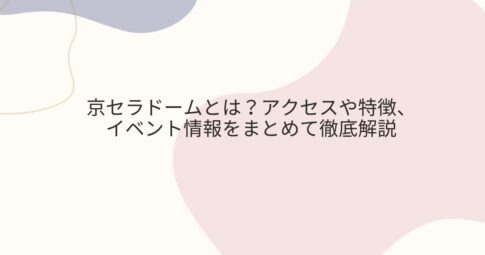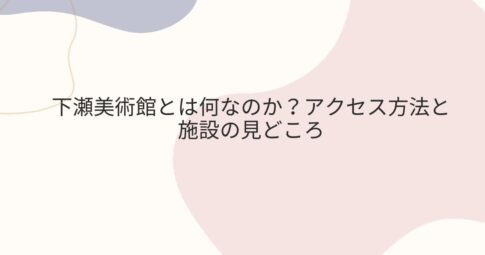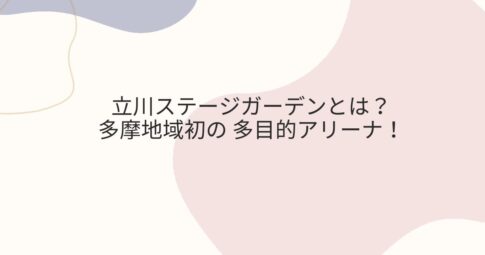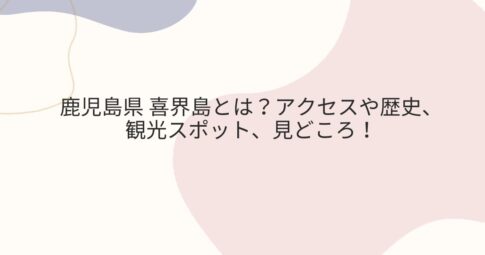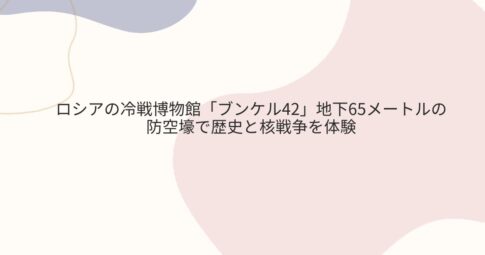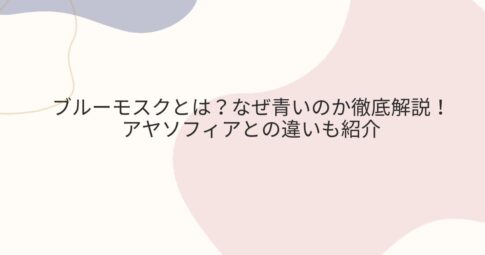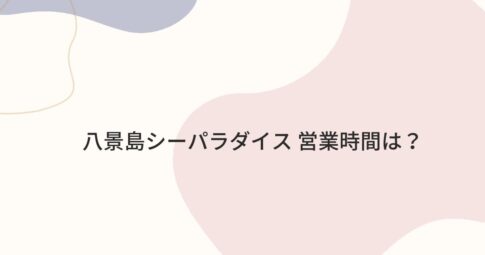はじめに
近年、世界中の観光地で深刻化している「オーバーツーリズム」。日本でも、京都や奈良といった古都から、最近では北海道・小樽市に至るまで、観光客の急増による様々な問題が発生しています。
この記事では、オーバーツーリズムの実態と、その対策について詳しく見ていきましょう。
オーバーツーリズムとは
映画「Love Letter」ロケ地の小樽市、観光客殺到でオーバーツーリズム深刻化 https://t.co/wb6S8Q3i0f
— cnn_co_jp (@cnn_co_jp) February 9, 2025
オーバーツーリズムとは、特定の観光地に観光客が過度に集中することで、地域社会や環境に悪影響を及ぼす現象を指します。具体的には、以下のような問題が挙げられます:
- 地域住民の日常生活への支障
- 環境破壊や文化財の損傷
- 地価や家賃の高騰
- 交通渋滞やゴミ問題
- 観光地としての魅力の低下
国内外の深刻な事例
小樽市の事例
映画「Love Letter」の舞台として知られる北海道・小樽市では、近年深刻なオーバーツーリズム問題に直面しています。
昨年は過去最高となる約9.9万人の外国人宿泊客を記録し、特に「船見坂」では以下のような問題が発生しています:
- 私有地への不法侵入
- 道路での危険な撮影行為
- ゴミのポイ捨て
- 交通妨害
これらの問題に対応するため、市は警備員の配置や警告看板の設置など、具体的な対策を講じています。
京都市の事例
古都・京都では、2015年に年間観光客数が5,684万人を記録。その後も増加の一途をたどり、以下のような問題が顕在化しています:
- 地価高騰による若者の転出
- 騒音や生活環境の悪化
- 舞妓へのパパラッチ行為
- 民泊トラブルの増加
世界の事例
世界的な観光都市でも同様の問題が報告されています:
- イタリア・ベネチア:年間2,200万人の観光客による混雑と住環境の悪化
- スペイン・バルセロナ:違法民泊の増加と地価高騰
- ペルー・マチュピチュ:遺跡保護のための入場制限の実施
解決に向けた取り組み
世界観光機関(UNWTO)は、オーバーツーリズム対策として11の提案を行っています。主な対策として:
- 観光客の時間的・空間的分散
- 新たな観光ルートの開発
- 地域コミュニティへの利益還元
- インフラ整備の改善
- 入場料や規制の導入
各地域でもユニークな取り組みが始まっています。例えば:
- ベネチア:団体観光客の人数制限と入場料徴収
- ポンペイ遺跡:1日の観光客数を2万人に制限
- 京都:観光スポットの分散化と時期による分散
これからの観光のあり方:まとめ
オーバーツーリズム問題の解決には、観光客、地域住民、行政の三者による協力が不可欠です。持続可能な観光の実現に向けて、以下の点が重要となります:
- 観光客のマナー向上と意識改革
- 地域の受入れ容量に応じた観光施策
- 地域住民の生活との調和
- 文化財や環境の保護
観光は地域経済の重要な柱である一方、行き過ぎた観光は地域社会に大きな負担をもたらします。
バランスの取れた観光開発を進めることが、今後の課題といえるでしょう。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪