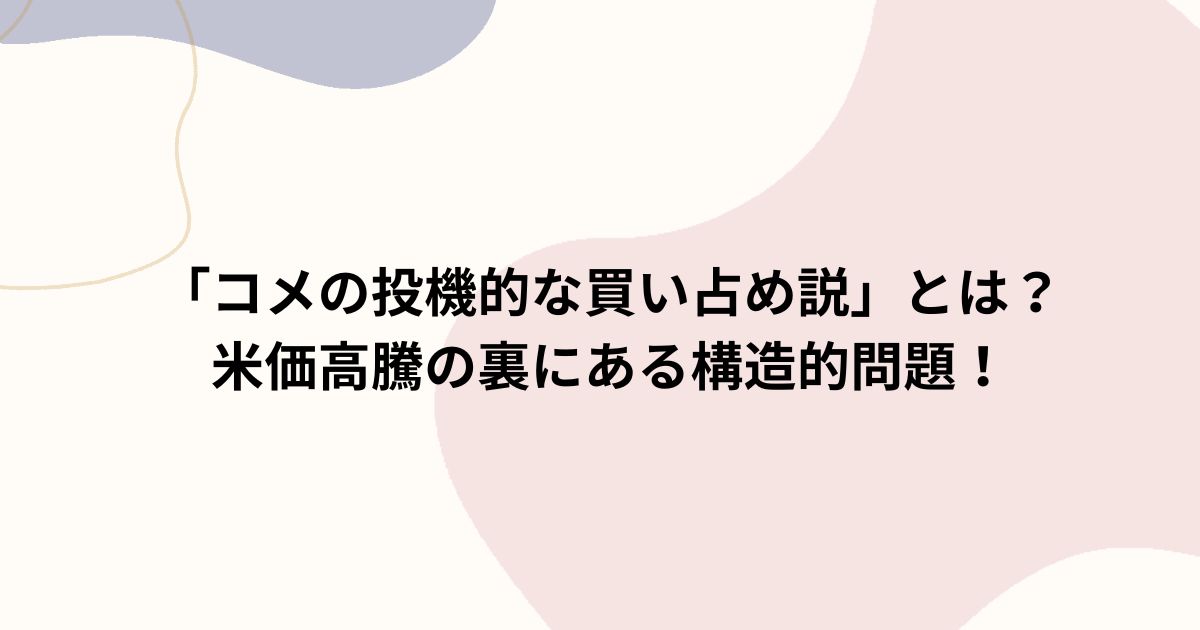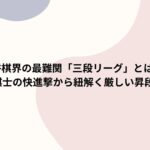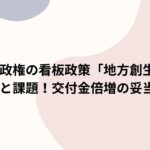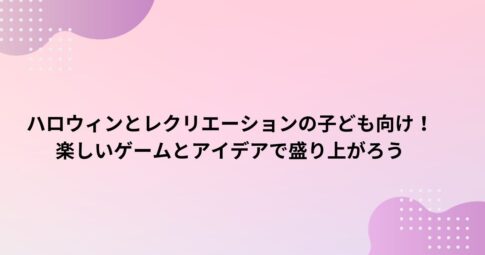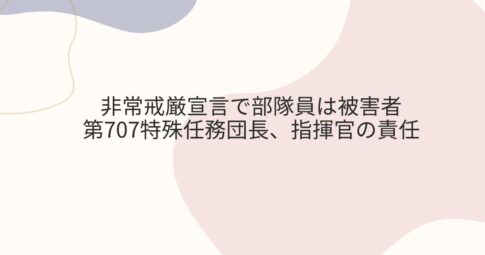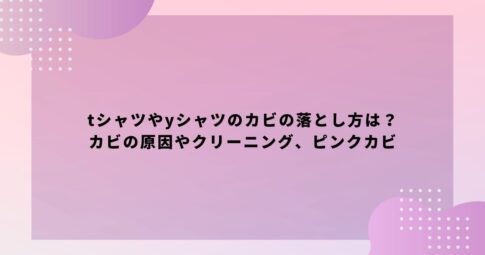はじめに
近年の米価高騰を巡り、農林水産省が展開する「投機的な買い占め説」が物議を醸しています。
この説によると、これまでコメを扱ったことのない新規参入者が大量の米を買い占め、価格つり上げを図っているとされています。
しかし、この説明には多くの疑問点が浮かび上がっています。
農水省が主張する「消えた21万トン」の謎
【農水省「コメの投機的な買い占め説」は胡散臭い…米価高騰の悲願を達成した「真犯人」の正体】https://t.co/cUnQ49AcuE
— ダイヤモンド・オンライン (@dol_editors) February 13, 2025
農水省は、大手卸業者の集荷量低下を根拠に、約21万トンものコメが従来の流通から消失したと主張しています。
これは一般家庭のお茶碗に換算すると約32億杯分に相当する膨大な量です。
農水省の江藤拓大臣は「米はある」と断言し、どこかに「スタック」されているとの見解を示しています。
実態は深刻な供給不足
しかし、データを詳細に分析すると、別の実態が浮かび上がってきます:
構造的な米不足の実態
- 2023年秋の主食用米収穫量:661万トン
- 年間需要量:705万トン
- 不足量:約40万トン
この数字が示すように、実際には40万トンもの供給不足が発生していました。
これは民間在庫の推移からも裏付けられています。2023年7月時点の在庫量は82万トンで、前年同期比で41万トン減少していました。
見過ごされる減反政策の影響
農水省が「投機的な買い占め」を強調する背景には、より根本的な問題から目を逸らせたい思惑があるとの指摘があります。
継続される実質的な減反政策
2018年に正式に廃止されたはずの減反政策ですが、実態としては「生産量の目安」という形で継続されています。
農水省は転作に対して補助金を支給し、実質的に主食用米の生産抑制を続けています。
生産量の意図的な抑制
- 2021年秋の収穫量:702万トン
- 2022年秋の収穫量:670万トン
- 減少要因:作付面積が5.2万ヘクタール減少
真の受益者は誰か
この状況下で最も恩恵を受けているのは、必ずしも農家や消費者ではありません。
JAを中心とした流通システムが、米価高騰による中間マージンの増加で利益を得ている構図が浮かび上がります。
2024年産米の相対取引価格は2万4665円と、2022年産の1万3920円から大幅に上昇しています。しかし、個人農家は肥料や燃料の高騰により、実質的な恩恵を受けられていない状況です。
「投機的な買い占め説」とは:まとめ
農水省が主張する「投機的な買い占め説」は、より本質的な問題から目を逸らすためのスケープゴートである可能性が高いと言えます。
食料自給率38%という状況下で、なお生産調整を続ける政策の妥当性こそが、真剣に議論されるべき課題なのではないでしょうか。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪