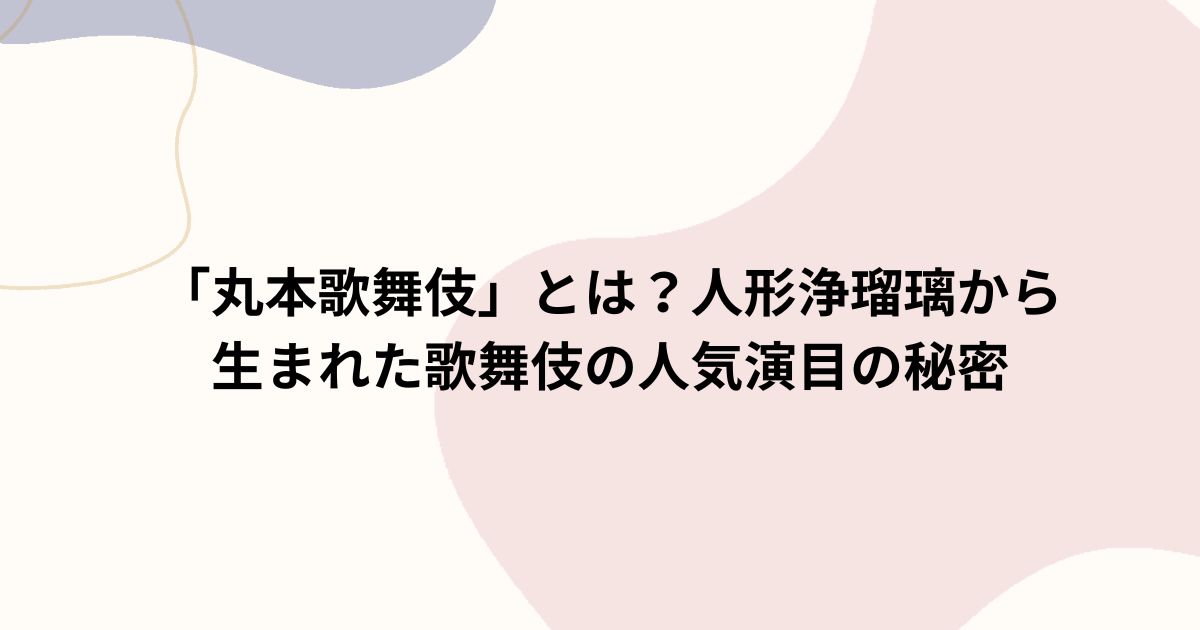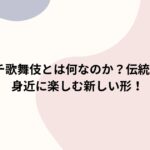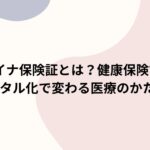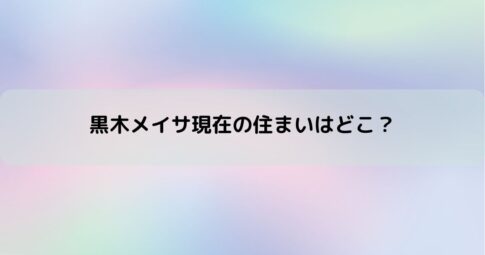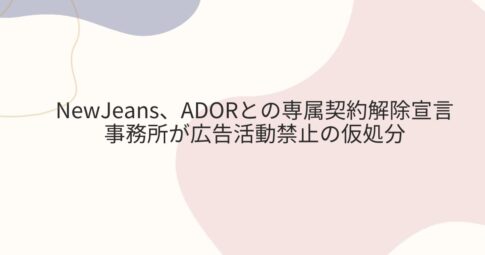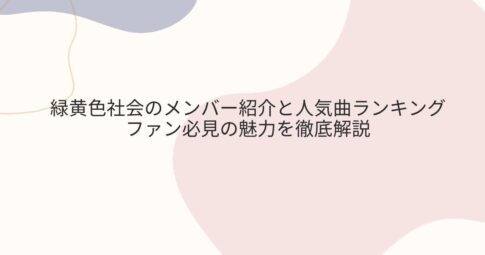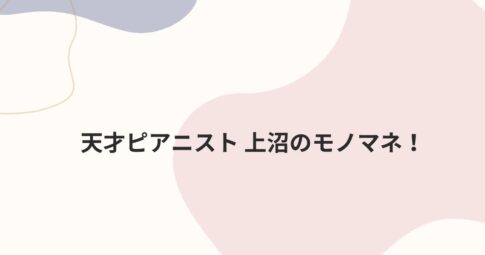はじめに
歌舞伎の世界には、「丸本歌舞伎」と呼ばれる特別なジャンルが存在します。今や歌舞伎の代表的な演目として知られる『仮名手本忠臣蔵』や『義経千本桜』なども、実はこの「丸本歌舞伎」に含まれています。
なぜ「丸本歌舞伎」が生まれ、どのような特徴を持っているのか、詳しく見ていきましょう。
人形浄瑠璃から歌舞伎へ:観客を魅了するための戦略
「丸本歌舞伎」は、歌舞伎の知名度アップのために生まれた!?【古典芸能 “好芸家” のススメ】(https://t.co/ArdHGZ5KNS)https://t.co/c3IzU8ZUmX#丸本歌舞伎 #歌舞伎座 #歌舞伎#竹本 #人形振り#壽初春大歌舞伎 #熊谷陣屋#新春浅草歌舞伎 #絵本太功記#令和7年初春歌舞伎公演… pic.twitter.com/hXYBF5o6ib
— 中村福助 (@fukusuke9_) January 7, 2025
18世紀中頃、歌舞伎界は人形浄瑠璃の人気に押されていました。そこで考え出されたのが、人形浄瑠璃の演目を歌舞伎に取り入れるという戦略でした。
1708年頃から始まったこの試みは、1715年に近松門左衛門の『国性爺合戦』が歌舞伎化されたことを契機に大きく広がっていきました。
「丸本」という名称は、浄瑠璃の台本全編を収めた版本に由来します。演劇評論家の戸板康二が「丸本歌舞伎」と名付けたこのジャンルは、単なる演目の移行以上の価値を生み出すことになりました。
「竹本」が支える独自の演出世界
歌舞伎専門の義太夫節演者
「丸本歌舞伎」の特徴として欠かせないのが「竹本」の存在です。義太夫節の開祖・竹本義太夫にちなんで名付けられた「竹本」は、歌舞伎専門の義太夫節演者として、物語を語る太夫と三味線方の役割を担っています。
俳優との絶妙な協演
人形浄瑠璃と異なり、「丸本歌舞伎」では役者自身が台詞を話します。「竹本」は役者の台詞以外の部分を語り、俳優の「型」に合わせて臨機応変に対応する高度な技術が求められます。
人間国宝の竹本葵太夫は、この役割を「刺身のわさび」に例え、作品を引き立てる重要な「部品」として表現しています。
独自の演出技法「糸に乗る」:まとめ
「丸本歌舞伎」最大の見せ場が「糸に乗る」という演出です。三味線のリズムに合わせて台詞を言い、演技を行うこの技法には、以下のような代表的な演出パターンがあります:
- 「物語」:過去の出来事を身振り手振りで語る場面
- 「クドキ」:主に女性役が心情を切々と語る場面
- 「人形振り」:人形浄瑠璃の動きを模倣する特殊な演出
これらの演出は、俳優と「竹本」の絶妙な連携によって成り立っており、「丸本歌舞伎」ならではの魅力を作り出しています。
現代では、新作歌舞伎の創作においても「竹本」が重要な役割を果たしており、歌舞伎の発展に欠かせない存在となっています。
人形浄瑠璃から生まれた「丸本歌舞伎」は、独自の演出表現を生み出し、今なお進化を続ける歌舞伎の重要なジャンルとして、観客を魅了し続けています。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪