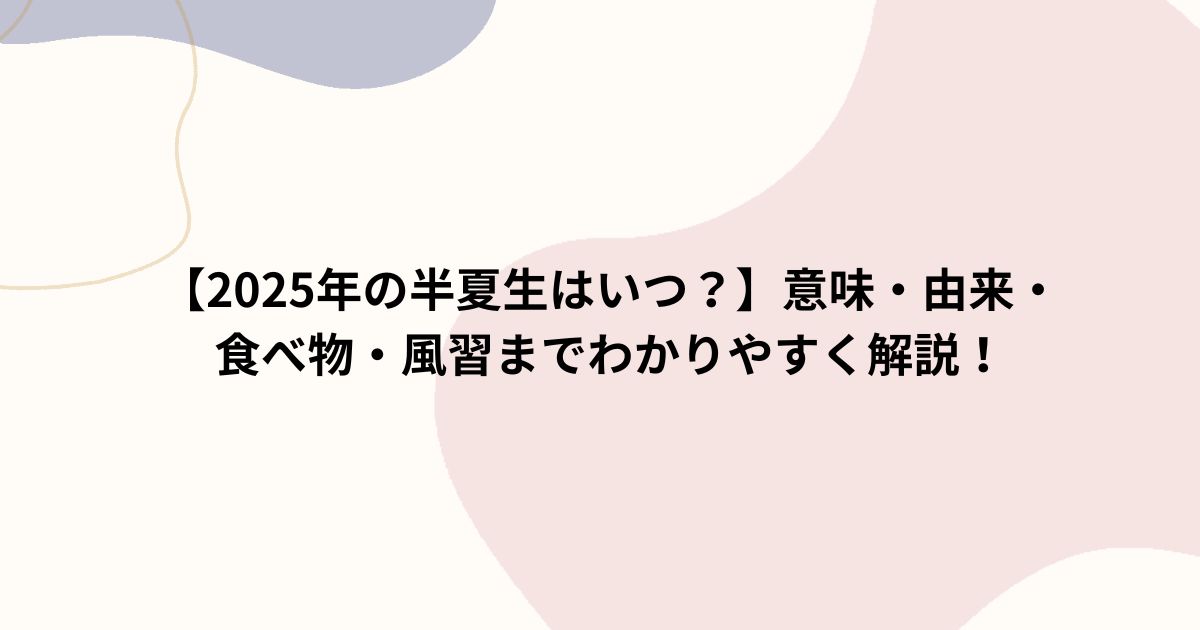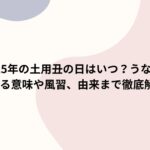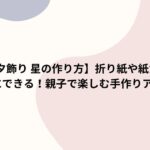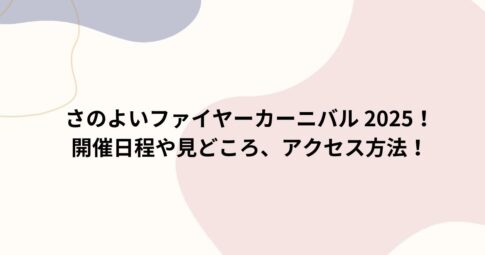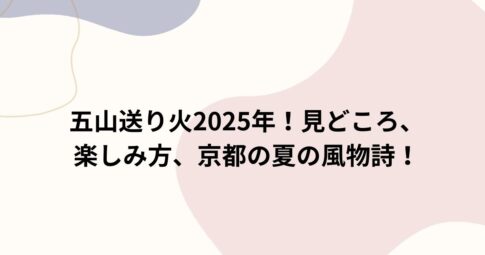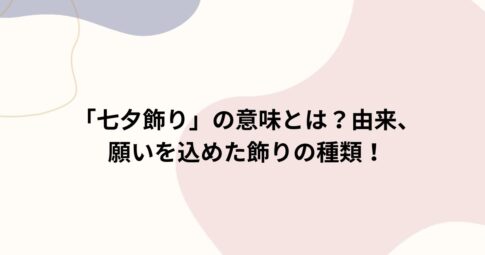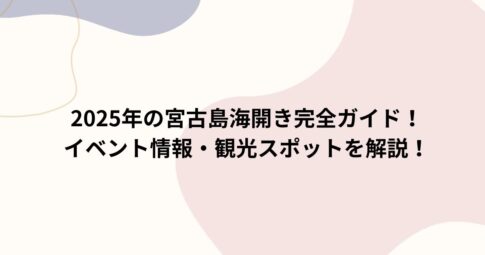はじめに
「半夏生(はんげしょう)」は、二十四節気や雑節の一つとして日本の季節行事に深く根付いています。特に農業や地域の風習と結びついており、「この日を過ぎたら田植えを終えるべき」とされてきました。
2025年の半夏生はいつなのか、そしてその意味や由来、各地での風習、食べ物などを詳しくご紹介します。暦の上では夏本番に突入するこの時期、半夏生を知ることで、日本の季節の深さにふれてみませんか?
2025年の半夏生はいつ?

引用元:天気予報
2025年の半夏生の日付
2025年の半夏生は「7月1日(火曜日)」です。
※年によって日付が変わるため、確認が必要です。
半夏生は、太陽の黄経が100度になる日を指し、夏至から数えて約11日目頃になります。暦の上では「雑節」の一つで、天体の動きに基づいて決まっています。
半夏生の意味と由来
名前の由来とは?
「半夏生」という言葉は、漢方植物「半夏(からすびしゃく)」が生え始める時期であることに由来しています。また、梅雨の終わりに差しかかる頃であり、気候や農作業の目安として重宝されてきました。
農業との深い関わり
古来より、半夏生を境に田植えを終えるのが良いとされてきました。「半夏生までに田植えを終えないと、実りが悪くなる」という言い伝えもあります。農家にとっては節目の日として重視されていたのです。
地域によって異なる半夏生の風習
関西地方の「タコを食べる」文化
関西では、半夏生にタコを食べる習慣があります。理由は、稲の根がタコの足のようにしっかり張るようにとの願いを込めて。スーパーでも「半夏生にはタコを!」とPOPが出るほどです。
福井県の「焼き鯖を食べる」風習
福井県では半夏生の日に焼き鯖を食べる習わしがあります。江戸時代に、田植えを終えた労をねぎらうために焼き鯖が振る舞われたのが始まりです。今でも伝統的な郷土食文化として受け継がれています。
その他の地域でも
一部地域では「うどん」や「餅」など、力のつくものを食べる風習があります。いずれも、暑さや疲労がたまりやすい時期に、栄養をしっかり摂るという目的があります。
現代における半夏生の楽しみ方
行事食を家族で楽しもう
タコや焼き鯖など、地域の行事食を家族で囲むことで、日本の風習を子どもたちに伝える良い機会になります。スーパーでも「半夏生フェア」などが開催されることがあります。
季節の変わり目として体調管理にも意識を
梅雨の終盤に当たるこの時期は、湿度が高く体調を崩しやすい季節でもあります。しっかり食べて、適度な休息を取ることで、夏を元気に迎える準備にもなります。
半夏生にまつわる豆知識
「半夏生=半夏生草」ではない?
「半夏生(はんげしょう)」という草も存在しますが、これは別名「カタシログサ」とも呼ばれる植物です。この草の名前が半夏生の時期と一致するため、混同されがちですが、由来は異なります。
実は七夕と近い!
半夏生の日は、七夕(7月7日)と近いため、地域によってはこの時期を一連の「夏の節目」として、さまざまなイベントや行事を合わせて行うこともあります。
2025年の半夏生:まとめ
2025年の半夏生は7月1日(火曜日)です。この日は古くから季節の節目として大切にされ、農業や食文化と深く結びついています。
関西ではタコ、福井では焼き鯖など、地域ごとに個性豊かな風習があり、現代でも親しまれています。
暑さが本格化する前に、体調を整える意味でも、半夏生の食文化を取り入れてみてはいかがでしょうか?
行事食を楽しみながら、日本の四季と暦の奥深さを感じてみてください。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪
- 2025年の土用丑の日はいつ?うなぎを食べる意味や風習、由来まで徹底解説!
- 【2025年の彼岸入りはいつ?】春彼岸・秋彼岸の意味や過ごし方を解説!