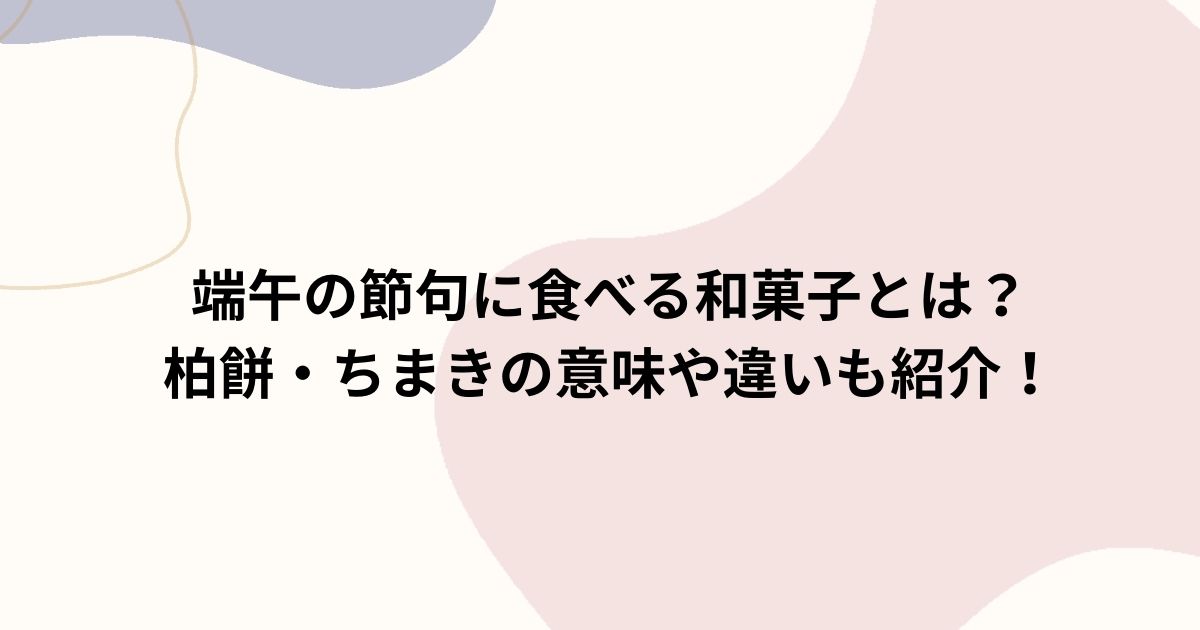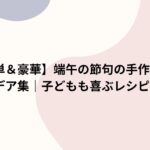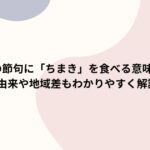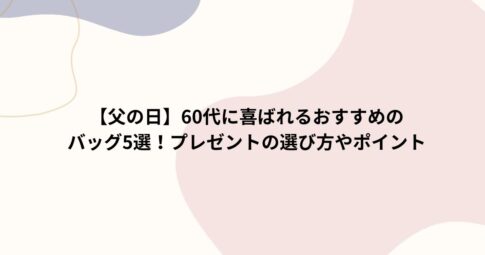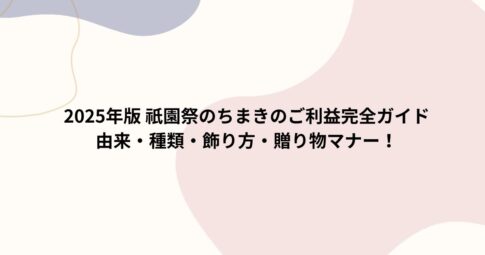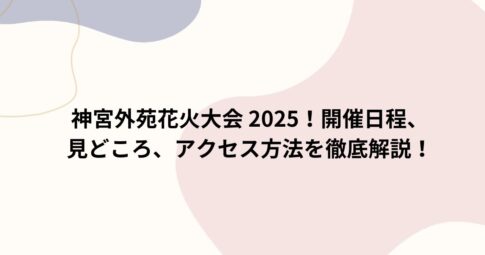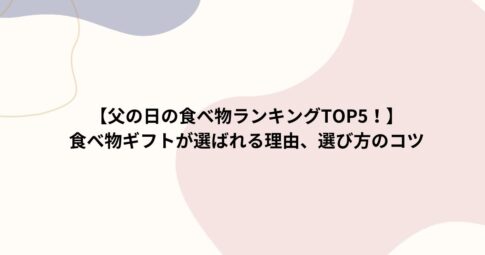はじめに
5月5日の端午の節句といえば、鯉のぼりや五月人形を思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、忘れてはならないのが「和菓子」の存在です。端午の節句には特別な意味をもつ和菓子を食べる風習があります。
この記事では、柏餅やちまきの由来や違い、さらには現代におすすめの和菓子について詳しく解説します。子どもの成長を祝う日に、伝統の味を改めて味わってみませんか?
端午の節句とは?背景と意味を簡単におさらい

引用元:tenki
5月5日は男の子の成長を祝う日
端午の節句は、古くから男の子の健康や成長を願う伝統行事として知られています。現代では「こどもの日」として祝われていますが、その歴史は中国にルーツをもち、日本では平安時代から行われてきたといわれています。
縁起をかついだ食べ物を食べる風習
端午の節句では、鯉のぼりや菖蒲湯とともに、縁起の良い和菓子を食べることで厄除けや繁栄を願うという文化が根付いています。中でも柏餅とちまきは代表的な存在です。
端午の節句に食べる和菓子:代表は「柏餅」と「ちまき」

柏餅の意味と由来
柏餅は、柏の葉で包んだ餅の中に餡が入っている和菓子で、主に関東地方で食べられます。柏の葉は「新しい芽が出るまで古い葉が落ちない」ことから、「家系が絶えない=子孫繁栄」を象徴しています。
また、柏の葉には防腐効果や殺菌作用もあり、食べ物を清潔に保つ意味もあるといわれています。
ちまきの意味と由来
ちまきは、もち米やうるち米を笹や竹の葉で包んだ食べ物で、関西地方や九州で多く見られる和菓子です。
由来は中国の詩人「屈原(くつげん)」を供養するためにちまきを川に流したという故事に基づき、厄除けや健康祈願の意味が込められています。日本では平安時代に伝わり、端午の節句の伝統食として定着しました。
地域による和菓子の違い
東日本では柏餅、西日本ではちまきが主流
日本全国で端午の節句に食べられている和菓子ですが、東西で食文化が大きく異なるのも特徴です。
- 関東地方 → 柏餅が一般的
- 関西・九州地方 → ちまきが多い
この地域差は、原材料の入手しやすさや文化の浸透度によるもので、今でも地方色が色濃く残っています。
中華風ちまきとの違い
「ちまき」と聞いて中華料理のもち米料理を思い浮かべる方もいますが、日本のちまきは和菓子であり、細長い円錐形が一般的です。甘いタイプが多く、あん入りのものや黒糖風味など、地域によって多彩な味わいが楽しめます。
現代風に楽しむ!端午の節句におすすめの和菓子3選
①よもぎ柏餅で春の香りを
よもぎ入りの柏餅は、春の季節感を味わえるおすすめの和菓子です。よもぎの香りと餡の甘さが絶妙にマッチし、目にも鮮やか。子どもにも人気の一品です。
②フルーツちまきで現代アレンジ
最近では、いちごやマンゴーなどを使った洋風ちまきも登場。見た目も可愛く、和菓子が苦手な子どもや若い世代にも喜ばれる工夫がされています。
③端午の節句限定の練り切り

和菓子店では、五月人形や鯉のぼりをかたどった練り切りや上生菓子も販売されています。季節感があり、プレゼントにもぴったり。華やかな席を演出してくれます。
端午の節句に食べる和菓子:まとめ
端午の節句に食べる和菓子には、子どもの健やかな成長を願う深い意味が込められています。
柏餅やちまきといった伝統の味を楽しむことで、古くから受け継がれてきた文化を次の世代にも伝えることができます。
地域や好みに合わせたアレンジ和菓子も増えている今、今年の端午の節句は、親子で和菓子を囲みながら、日本の行事を楽しんでみてはいかがでしょうか?
最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪
- 【祖父母必見】端午の節句のお祝い、孫への素敵な贈り方とマナーとは?
- 【兜は誰が買う?】端午の節句のしきたりと現代の事情をわかりやすく解説!
- 端午の節句のお祝い金、相場はいくら?渡し方やマナーも徹底解説!