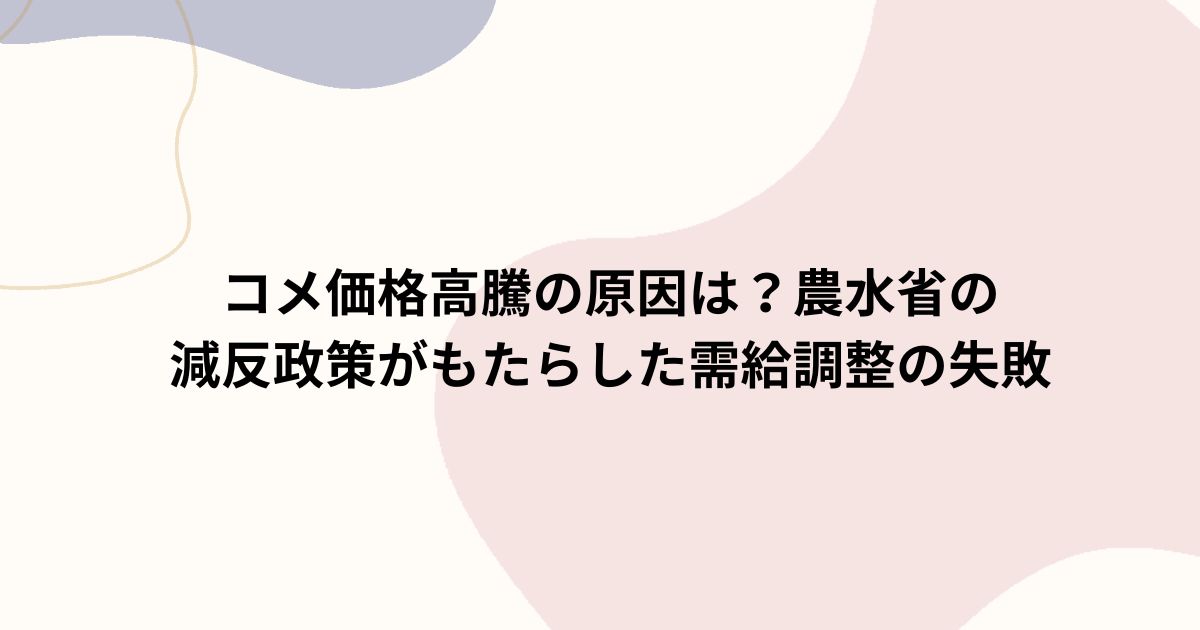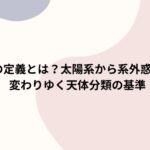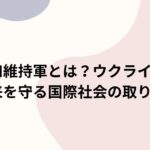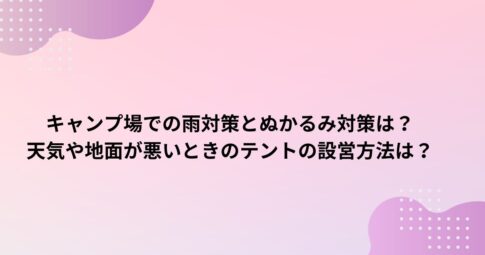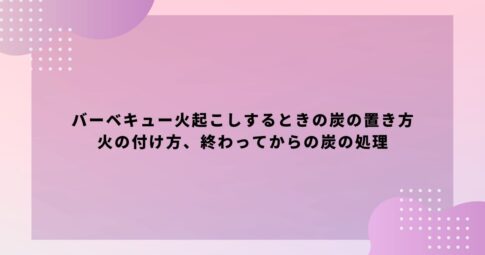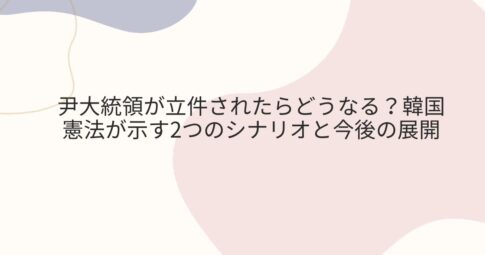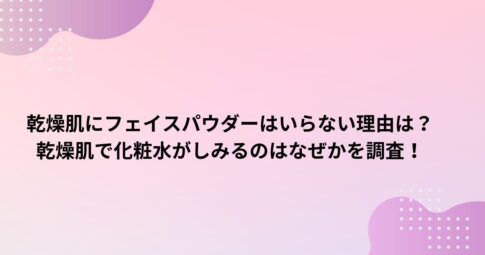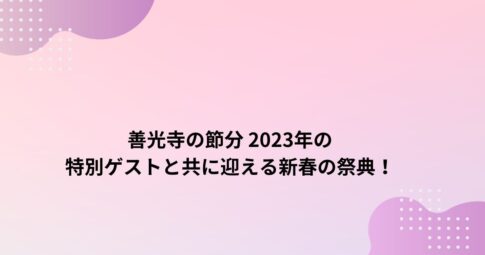はじめに
2024年、日本の食卓を揺るがす異常事態が続いています。コシヒカリ5kgが4000円を突破するなど、米価の高騰が深刻な社会問題となっています。
この状況を受け、農水省は備蓄米21万トンの放出を決定しましたが、この対症療法的な対応は、実は農水省自身が作り出した構造的問題の表れと言えるでしょう。
コロナ禍からの政策の迷走
「農水省が諸悪の根源」コメ高騰の真犯人“減反政策で需要ギリギリ”“スーパーに卸すより外食産業”関係者が明かす実態#SmartFLASH #コシヒカリ #コメ #スーパー #市場 #政府https://t.co/ewOQhyDLxg
— SmartFLASH (@info_smafla) February 17, 2025
需要予測を誤った減反政策
2020年のコロナ禍で、外食産業の休業を余儀なくされた結果、米の在庫が大幅に増加し、価格が暴落しました。
当時、60kgあたりの卸売価格は1万円を下回る地域も出現。農家の経営を圧迫する事態となりました。
この状況に対し、農水省は主食用米から飼料用米への転作を推進。
補助金を積み増すことで、2021年から2022年にかけて飼料用米の作付面積は過去最高の14万ヘクタールにまで拡大しました。
しかし、この政策が今日の米不足を引き起こす伏線となったのです。
市場構造の歪みが生んだ供給不足
民間流通への シフト
減反政策により需要予測ギリギリまで生産量を抑制された状況下で、米農家の間で新たな動きが生まれました。
全農や農協経由での販売から、民間の米卸業者への直接販売にシフトする農家が増加したのです。現在、農協と全農の取扱高は全国平均で50%程度まで低下しています。
外食優先の流通構造
さらに問題を複雑にしているのが、民間業者による流通の偏りです。高値で仕入れた米は、スーパーマーケットよりも外食産業に優先的に供給される傾向にあります。その理由として:
- 外食産業は米がなければ営業継続が困難
- 病院や学校給食など公共施設への供給責任
- スーパーの買いたたき体質への反発
- 小売店は商品の代替が可能
という構造的な要因が挙げられます。
政策の歪みが引き起こす市場混乱
2024年の主食用米の収穫量は679万トンと、前年比18万トン増を記録し、6年ぶりの増産となりました。
しかし、生産量と需要の差約39万トンが正常な流通から外れ、どこかに「備蓄」されている状況です。
これは生産量の5%弱に相当し、需要ギリギリの生産量では、この程度の流通の歪みでも深刻な供給不足を引き起こすことになります。
農水省による備蓄米の放出は、価格高騰に対する初めての対策となりましたが、これは根本的な解決策とはなりえません。
むしろ、減反政策による生産調整と、それに伴う市場構造の歪みこそが、現在の米価高騰の本質的な原因といえるでしょう。
今後、安定的な米の供給と適正価格の維持のためには、農水省による需給調整政策の抜本的な見直しが必要不可欠です。
生産者、流通業者、消費者のバランスの取れた利益を考慮した新たな政策フレームワークの構築が求められています。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪