はじめに
一年の中で最も昼が長くなる「夏至」。太陽が最も高く昇り、地域によっては夕方遅くまで明るい時間が続きます。
夏至は日本だけでなく、世界各地で特別な意味を持つ日とされ、伝統的な行事や食べ物とも深い関わりがあります。
本記事では、夏至の日の出・日の入りの時間の変化や、日本各地で食べられる夏至の特別な食べ物について詳しく紹介します。
「夏至」とは
「夏至」とは、「二十四節気」のひとつ。太陽が最も北に寄り、北半球では昼が一番長い日です。
北極では太陽が沈まず、太陽が現れない。今年は6月21日が夏至です。
「二十四節気」とは!「正節」とは!

「二十四節気」とは
「二十四節気」とは、①~㉔までをいいます。「春夏秋冬」の4等分する暦のようなものとして考案された区分手法の一つです。
春は①~⑥です。
①立春(りっしゅん)2月4日頃
②雨水(うすい)2月19日頃
③啓蟄(けいちつ)3月6日頃
④春分(しゅんぶん)3月21日頃
⑤清明(せいめい)4月5日頃
⑥穀雨(こくう)4月5日頃
⑦~⑫が夏です。
⑦立夏(りっか)5月5日頃
⑧小満(しょうまん)5月21日頃
⑨芒種(ぼうしゅ)6月5日頃
⑩夏至(げし)6月21日頃
⑪小暑(しょうしょ)7月7日頃
⑫大暑(たいしょ)7月23日頃
⑬~⑱が秋です。
⑬立秋(りっしゅう)8月7日頃
⑭処暑(しょしょ)8月23日頃
⑮白露(はくろ)9月8日頃
⑯秋分(しゅうぶん)9月23日頃
⑰寒露(かんろ)10月8日頃
⑱霜降(そうこう)10月23日頃
⑲~㉔が冬です。
⑲立冬(りっとう)11月7日頃
⑳小雪(しょうせつ)11月22日頃
㉑大雪(たいせつ)12月7日頃
㉒冬至(とうじ)12月22日頃
㉓小寒(しょうかん)1月5日頃
㉔大寒(だいかん)1月20日頃
春は①~⑥です。⑦~⑫が夏です。⑬~⑱が秋です。⑲~㉔が冬です。
24の「節気」は、①〜㉔までをいいます。
一年を12の「節気」と12の「中気」に分類し、さらに季節を表す名前が付けられています。
<日の出が一番早いのは夏至じゃない>
— ウェザーニュース (@wni_jp) June 12, 2022
今年は6月21日に二十四節気「夏至」を迎えます。夏至は一年で昼の時間が最も長くなる日です。しかし、日の出時刻が最も早く、日の入り時刻が最も遅くなるわけではありません。
じつは今頃が日の出が一番早い時期にあたります。https://t.co/TARTrZ69Eq pic.twitter.com/gri9L3NguG
「正節」とは
「正節」とは①〜㉔の奇数をいいます。
「中気」とは
「中気」とは①〜㉔の偶数をいいます。
春は①~⑥です。
①立春(りっしゅん)2月4日頃 ②雨水(うすい)2月19日頃 ③啓蟄(けいちつ)3月6日頃
④春分(しゅんぶん)3月21日頃 ⑤清明(せいめい)4月5日頃 ⑥穀雨(こくう)4月5日頃
⑦~⑫が夏です。
⑦立夏(りっか)5月5日頃 ⑧小満(しょうまん)5月21日頃 ⑨芒種(ぼうしゅ)6月5日頃
⑩夏至(げし)6月21日頃 ⑪小暑(しょうしょ)7月7日頃 ⑫大暑(たいしょ)7月23日頃
⑬~⑱が秋です。
⑬立秋(りっしゅう)8月7日頃 ⑭処暑(しょしょ)8月23日頃 ⑮白露(はくろ)9月8日頃
⑯秋分(しゅうぶん)9月23日頃 ⑰寒露(かんろ)10月8日頃 ⑱霜降(そうこう)10月23日頃
⑲~㉔が冬です。
⑲立冬(りっとう)11月7日頃 ⑳小雪(しょうせつ)11月22日頃 ㉑大雪(たいせつ)12月7日頃 ㉒冬至(とうじ)12月22日頃 ㉓小寒(しょうかん)1月5日頃 ㉔大寒(だいかん)1月20日頃
日の出の時間と日の入りと日照時間は?
山口県の日の出の時刻は5:04
日の入り時刻は19:29
日照時間は14h26m
サンシーカーで2022年6月21日の太陽の位置(軌道)を見る
サンシーカー写真
・緑色のラインが水平線(地平線)
・黄色のラインが太陽の軌道
・黄色の数字が時間、赤色の数字が日時、黄色の丸いのが太陽。
緑色のラインと黄色のラインの交差する点が、日の入り・日の出。
夏至に何を食べる風習があるのだろうか?
日本では、夏至は農作業が最も忙しい時期であることもあり、全国的な風習はないようです。
冬至にかぼちゃを食べるように夏至は、何を食べるかは、地方によってまちまちです。
関西地方ではタコの8本足のように稲が深く根を張ることを祈願してタコを食べます。
愛知県では、無花果(イチジク)の田楽を食べるようです。
静岡県では、冬瓜を食べる風習があり、新小麦で焼餅をつくり神に供える風習があり、豊作を祈願するものです。
田作を手伝ってくれる近所に配る場合もあるようです。関東で多いですが島根県や熊本県でも同様の行事が行われています。
夏至とは:まとめ
今回は、夏至とは?日の出の時間と日の入りと日照時間は?夏至に何を食べる風習があるのだろうか?という事を解説しました。
夏至とは一年中で昼時間が一番長い日であり、夜時間が一番短い日である、と言われています。
夏至から冬至に至るまで1日に何分づつか短くなっていくといわれています。
夜時間が短くなっていくんですね。
昼時間が一番長いと言われている夏至を大事に過ごせたらいいですね。
最後までお読みいただきましてありがとうございます。(^^♪





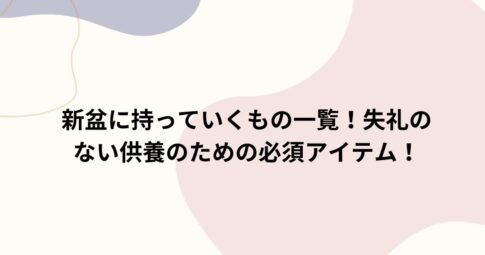










地震が来たらどうすればいいのか?備えと対策を徹底調査!
惑星直列とは?意味やいつからいつまで始まるのか惑星パレード調査