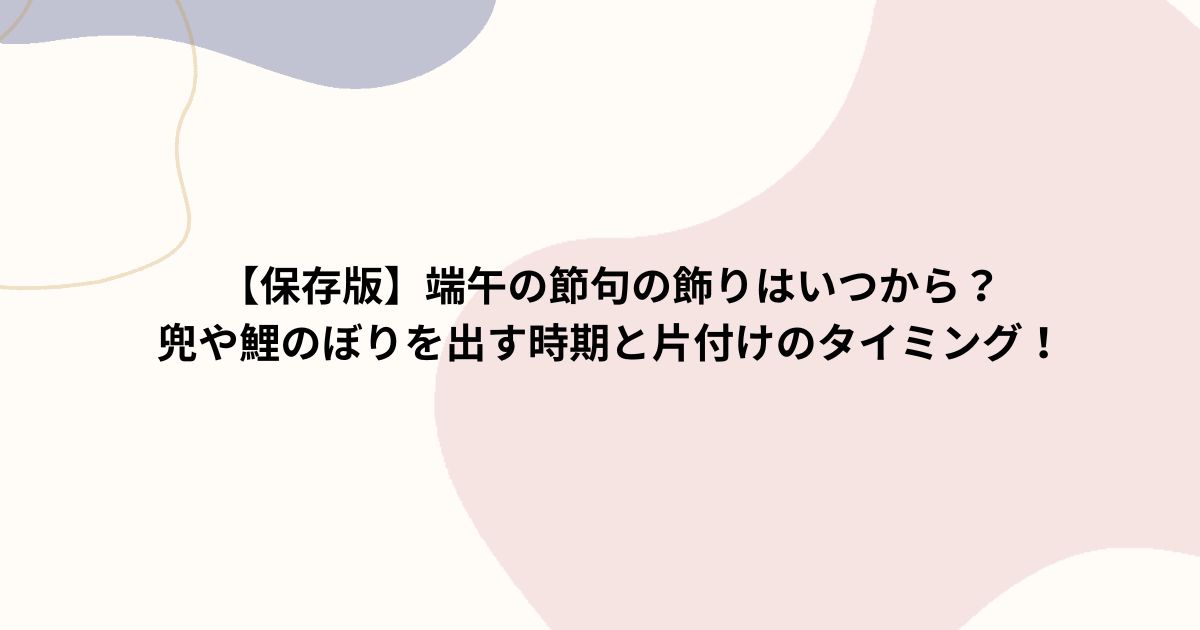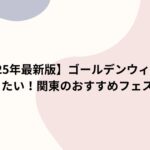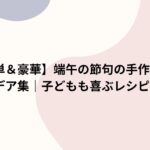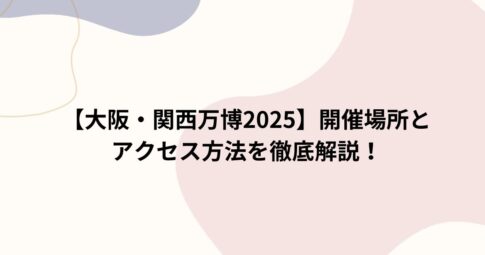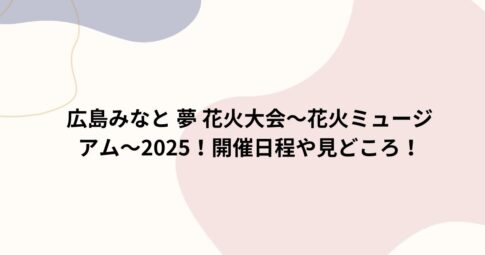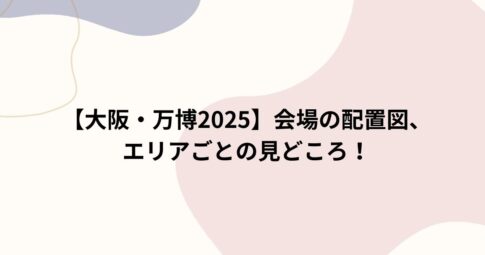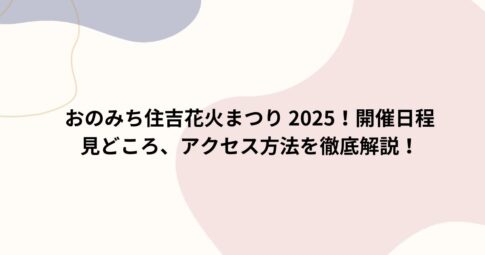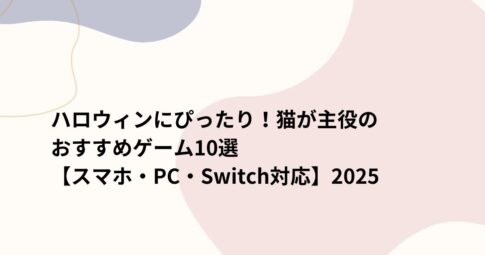はじめに
5月5日の端午の節句は、男の子の健やかな成長を願う日本の伝統行事。その象徴ともいえる兜飾りや鯉のぼりは、いつから飾るべきか迷う方も多いのではないでしょうか?
本記事では、端午の節句の飾りを出すタイミングや意味、片付けの注意点までをわかりやすく解説します。初節句を迎えるご家庭にも役立つ情報満載です!
端午の節句の飾りはいつから出す?

一般的には「春分の日の後〜4月中旬」が目安
端午の節句の飾りは、春の訪れを感じる春分の日(3月20日ごろ)以降〜4月中旬にかけて飾り始めるのが一般的とされています。これは、季節の節目にふさわしく、春の厄払いとしても意味を持つためです。
遅くても「4月下旬」には飾りたい理由
ギリギリになって4月末に飾るケースもありますが、「一夜飾り」は避けたいところ。節句当日の直前に出すのは縁起が悪いとされるため、少なくとも1週間前までには飾るのが理想的です。
地域によって飾り出しの時期が異なることも

関東と関西では若干の違いあり
関東では3月末〜4月初旬に飾り始めるご家庭が多い一方で、関西では4月中旬以降に出すこともあります。
地域の風習や家族の予定に合わせて、柔軟に対応してもOKです。
初節句の場合は早めに用意を
初めての節句では、両親や祖父母から兜や鯉のぼりを贈られるケースが多く、準備に時間がかかることも。余裕を持って3月中に準備を始めておくと安心です。
端午の節句の飾りにはどんな意味がある?
兜飾り:身を守る願いが込められている
武将が戦いで身を守るためにかぶる兜には、「病気や災いから子どもを守る」という願いが込められています。立派な兜には、将来立派に成長してほしいという願いも。
鯉のぼり:出世の象徴
滝を登る鯉のように、どんな困難にも立ち向かい、立派に成長してほしいという願いが込められています。外に飾るのが一般的ですが、最近ではベランダ用や室内用のミニ鯉のぼりも人気です。
飾りを片付けるタイミングと注意点
片付けは5月5日以降、天気の良い日を選んで
節句が終わったら、5月5日〜10日頃を目安に片付けるのが一般的です。湿気の多い日は避け、晴れた日に丁寧に乾燥させて収納することで、来年も綺麗に飾ることができます。
長期間出しっぱなしにしない理由
長く飾り続けてしまうと、「子どもが家に居ついてしまう」といった縁起を担いだ言い伝えもあります。季節行事として区切りをつけ、節目を大切にしましょう。
片付けのコツと収納アイデア
兜や鯉のぼりは湿気と直射日光に注意
・防虫剤を入れる
・布で包む、または専用ケースに戻す
・風通しの良い場所に保管する
特に木製の台座や装飾品はカビや虫食い対策が重要です。
次回も気持ちよく飾れる工夫を
収納時に簡単なメモ(どの部品がどこにあったか)を入れておくと、翌年の組み立てがスムーズ。写真を撮っておくのもおすすめです。
端午の節句の飾りはいつから:まとめ
端午の節句の飾りは、3月中旬〜4月中旬ごろに出すのがベスト。遅くとも4月末までに飾り、5月5日を過ぎたら晴れた日に丁寧に片付けましょう。
兜や鯉のぼりは、子どもの健やかな成長と出世を願う大切なシンボル。地域の習慣を尊重しながら、家族の節句を心から楽しんでくださいね。
最後までお読み頂きましてありがとうございました。(^^♪
- 端午の節句に食べる和菓子とは?柏餅・ちまきの意味や違いも紹介!
- 【祖父母必見】端午の節句のお祝い、孫への素敵な贈り方とマナーとは?
- 【兜は誰が買う?】端午の節句のしきたりと現代の事情をわかりやすく解説!